
健康診断を受けた後、「要再検査」や「要精密検査」という結果通知に不安を感じる人は少なくありません。
判定の違いやそれぞれの意味、対応の重要性を知ることにより、必要な検査の検討や生活改善を進めやすくなります。
この記事では、健康診断の診断結果の見方や要再検査・要精密検査の違い、再検査が必要になった場合の具体的な行動、指摘されやすい検査項目ごとの例などについて紹介します。
健康診断の要再検査・要精密検査について詳しく知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
健康診断の結果はどう見るのか
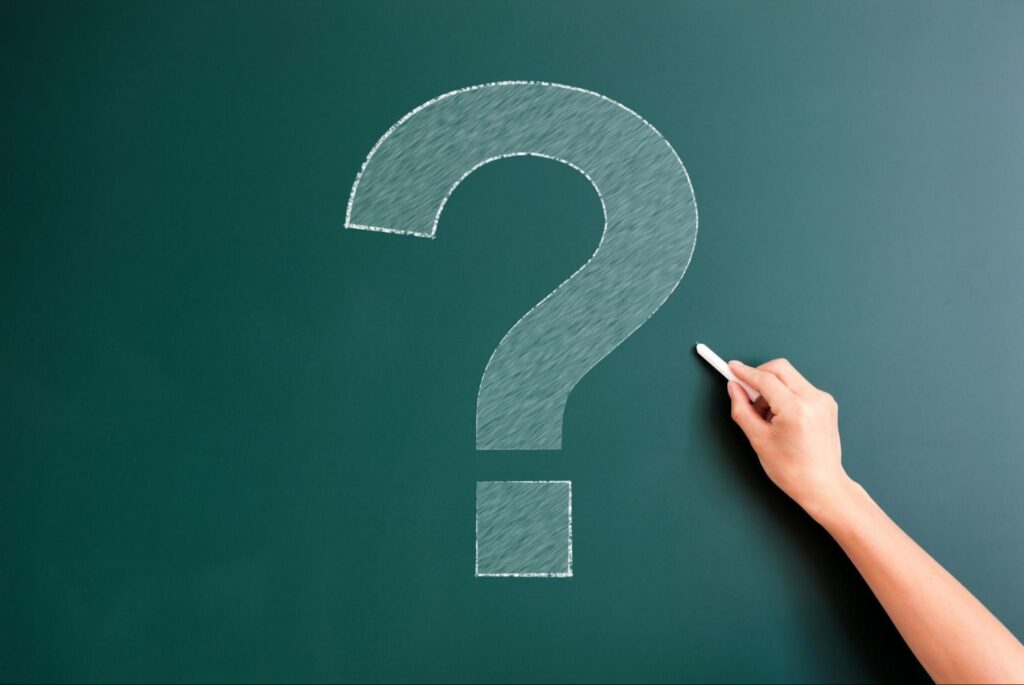
健康診断の判定区分には「異常なし」から「要治療」まで複数の段階があり、それぞれの意味や推奨する対応が異なっています。
以下の表は「異常なし」から「要治療」まで、それぞれの区分と推奨する対応例をまとめたものです。
| 判定区分 | 意味 | 対応 |
|---|---|---|
| 異常なし | 検査項目がすべて基準範囲内。健康状態に問題がない | 次回健診まで現状維持。 |
| 要経過観察 | 軽度の異常やわずかな基準値超過があるが、ただちに治療が必要な状態ではない。 | 生活習慣の見直しと次回健診で経過を確認。 |
| 要再検査 | 測定誤差の可能性があるため、同じ検査を再度実施の上、再確認。 | 医師の指示に従い、同じ検査を受ける。 |
| 要精密検査 | 病気や明らかな異常が疑われる。より専門的な検査で正しい診断が必要。 | 医療機関を受診し、精密検査を受ける。 |
| 要治療 | 明らかな病気や治療を要する異常が認められる。 | 医療機関を受診し、速やかに治療を開始する。 |
「要治療」は、すでに病気が進行している恐れもある状態です。
「要再検査」「要精密検査」は必要であれば早期治療を含めた対策を進められる重要な段階にあたるため、該当したらすぐに行動することを強くおすすめします。
なお、上表はあくまで一例です。健康診断を受けた医療機関によって表記方法や項目名が異なる場合があります。
『要再検査』と『要精密検査』の違い

健康診断で「要再検査」や「要精密検査」という判定を受けた時、それぞれの違いが分かりにくいかもしれません。
ここでは、要再検査と要精密検査の違いについて具体的に紹介します。
要再検査
要再検査は、一時的な体調変化や日常生活の影響、検査時の偶発的な要因などで基準値を外れた場合に通知されるものです。
例えば、前日の過度な飲食や睡眠不足、運動、緊張状態などにより検査結果が一時的に変動する場合があります。
要再検査と判定された場合は、同じ検査を再度受けて本当に異常があるかどうかを確認します。
再検査の内容は初回健診と同様で、特別な準備が不要なことが多く、負担も少ないケースが多いです。
再検査で問題がなければ経過観察になりますが、再び異常が認められた場合や別の疾患が疑われる場合は精密検査に進む場合もあります。
要精密検査
要精密検査は、検査値に明らかな異常や病気が強く疑われる場合に通知されます。
前述の再検査とは異なり、より詳しい検査や専門的な診断が必要とされる状態です。
例えば、血液検査や画像検査の結果から重大な病気の可能性が考えられる場合、超音波検査やCT、MRI、内視鏡検査など、より高度な医療機器や専門医による診断が求められます。
要精密検査になったら放置せず、できるだけ早く専門医を受診し、精密検査を受けてください。
再検査・要精密検査と言われたら

健康診断で「再検査」や「要精密検査」と通知された場合、二次検診の受診を強くおすすめします。
ここでは、二次検診の受診先や受診方法、費用などについて紹介します。
二次検診を受ける
健診機関から再検査や要精密検査の通知が届いたら、自己判断で放置せず、できるだけ早く二次検診を受けましょう。
最初の健康診断で異常が指摘されても、一時的な体調や外部要因で数値が変動する場合があります。
再検査ではその変動が一過性なのか、あるいは継続した異常なのかを確認します。
また、要精密検査は、さらに詳しい検査によって病気の有無や原因を特定するために必要です。
それぞれの結果で異常が再度認められた場合には、治療やほかの検査が必要になることもあります。
二次検診を受ける場所
二次検診は基本的に最初に健診を受けた医療機関で再検査を受けることが一般的ですが、指定医療機関がある場合や、かかりつけ医に相談するケースも見られます。
しかし検査内容によっては、該当する項目を検査できる設備が整った施設を案内されることもあるため、案内に従い、指定された医療機関に予約を入れましょう。
特に指定がない限り、自身が希望する医療機関で受診しても問題ありません。
どこで二次検診を受けるべきか分からない場合には、お勤め先の産業医や医療機関へ問い合わせるとアドバイスをもらえるでしょう。
二次検診は何科へ行くべき?
二次検診で受診する診療科は、健康診断の検査項目ごとに異なります。
通知書や医療機関の案内にも診療科の記載がありますが、不明な場合は健診機関やかかりつけ医に事前に相談するとよいでしょう。
以下は二次検診先の一例です。
| 要再検査・要精密検査対象 | 診療科 |
|---|---|
| 便潜血検査 | 内科・消化器 |
| 胸部X線検査 | 呼吸器内科 |
| 腎機能検査 | 腎臓内科、泌尿器科 |
| 肝機能検査 | 内科・消化器、肝臓内科、 |
| 糖尿病検査 | 糖尿病内科、内分泌内科 |
このほか、疑われる症状に合った診療科で二次検診を受けましょう。
二次検診の費用目安
二次検診の費用は、検査内容や受診する医療機関によって異なりますが、一般的な再検査であれば数千円から1万円程度が目安です。
精密検査の場合、CTやMRI、内視鏡など高度な検査を追加することで費用がかかることもあります。
ただし、要再検査・要精密検査となった場合の検査は原則として保険が適用されます。
高額療養費制度や会社の補助制度が利用できることもあるため、負担を理由に検査を先送りにせず、適切な窓口へ相談しましょう。
【重要】自己判断で二次検診を先送りしない
再検査や精密検査の通知を受け取った場合、自己判断で放置したり先延ばしにしたりすることはおすすめできません。
実際に大腸がん検診(便潜血検査)で要精密検査になったものの、内視鏡検査(大腸カメラ検査)を「受ける予定なし」と考えている人が約8.5%いるとの調査結果があります。
(参考:胃・大腸がん検診と内視鏡検査に関する意識調査白書2024|OLYMPUS)
ライフスタイルや仕事の都合で、要再検査や要精密検査に対応できない事情はあるかもしれませんが、検査を受けないことで重大な疾患の発見が遅れるリスクが高まります。
健康診断は早期発見・早期治療につなげるための重要な機会です。
万が一、検査で異常が見つかった場合でも、適切な対応をすることで重症化を防ぎやすくなります。
例えば、大腸がんは早期発見・早期治療により90%以上の治癒率が期待できる病気です
ほかの病気も同様で、発見や治療が早ければ早いほど治癒率の向上が見込めるため、要再検査・要精密検査の通知が来たら、可能な限り早く医療機関を受診してください。
健康診断で要再検査・要精密検査を指摘されやすい項目は?

健康診断ではさまざまな検査項目がありますが、特に要再検査・要精密検査を指摘されやすい項目もあります。
ここでは、血圧、血糖値、コレステロール、肝臓、便潜血など、要再検査・要精密検査の対象になりやすい項目について紹介します。
なお、紹介するのはあくまで一例です。このほかの項目が要再検査・要精密検査になることもあります。
血圧
血圧は特に高血圧が多いです。高血圧が続くと、脳卒中や心筋梗塞などのリスクが高まります。
ただし、基準値から外れる場合、一時的な体調や緊張、測定環境の影響で数値が上昇していることも少なくありません。
しかし、再検査で継続的に高い血圧が確認されれば、生活習慣の改善や降圧薬の使用が検討されます。
極端な高血圧や合併症が疑われる場合は要精密検査になり、心臓や腎臓の機能を詳しく調べる追加検査や専門医への紹介が必要になるケースもあります。
血糖値
血糖値は前日の食事や体調に左右されることもあり、最初の異常が一過性である可能性も否定できません。
しかし、血糖値の異常確認は糖尿病の早期発見につながり、基準値から外れた場合、多くの患者さんは再検査がすすめられます。
再検査でも高い血糖値が続いていた場合や、随時血糖・HbA1cなどほかの検査で異常が重なった場合には要精密検査に進み、糖尿病やその予備群と診断されることがあります。
糖尿病は放置すると合併症のリスクが高まるため、指示された追加検査や生活改善指導があれば速やかに取り組みましょう。
コレステロール
コレステロール値では総コレステロール、LDL(悪玉)、HDL(善玉)、中性脂肪のバランスが重視されます。
LDLコレステロールや中性脂肪が高い場合、動脈硬化や心血管疾患のリスクが高まるため、基準値から外れていると再検査が必要です。
再検査でも異常が認められる場合や、ほかの危険因子と重なる場合には要精密検査の対象になります。
また、専門医による詳細な血液検査や動脈硬化の有無を調べる検査が追加されることも多いです。
肝臓
肝臓の項目では、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなどの異常が見られた場合、再検査・精密検査が必要となることがあります。
肝臓の異常は放置すると肝炎や肝硬変、脂肪肝など重篤な疾患のリスクが高まるため、やはり再検査・要精密検査は積極的に受けましょう。
肝機能の軽度な異常は、一時的な疲労や飲酒の影響でも起こりやすいため、まずは再検査で経過を確認します。
繰り返し異常が出る場合や数値が著しく高い場合は要精密検査になり、腹部エコーやウイルス検査など詳細な検査が行われます。
便潜血
便潜血検査は、消化管の出血や大腸がん、ポリープなどの早期発見に用いられる検査です。
便潜血検査の結果が陽性になる原因には、一時的な腸炎や痔、食事の影響なども含まれますが、大腸がんのような深刻な疾患の可能性も否定できません。
検査で陽性になった場合には、自己判断で放置せず、医師の指示に従い追加検査を受けましょう。
陽性と判定された場合、大腸カメラによる精密検査が必要になります。
精密検査では内視鏡を用い、大腸内の異常がないかを詳細に調べます。自覚症状がなくても早期の病変が見つかることがあるため、指摘を受けた際には確実に精密検査を受けてください。
当院、広尾クリニック内科・消化器では、専門医・指導医による苦痛に配慮した下部内視鏡検査(大腸カメラ検査)を受けていただけます。再検査・要精密検査が必要になった際には早めにご相談ください。
まとめ
健康診断で「要再検査」や「要精密検査」と指摘された場合は、通知内容や指示を正しく理解し、可能な限り早く二次検診を受けることをおすすめします。
二次検診先は最初の健康診断を受けた医療機関のほか、状況に応じて変わるケースもあるため、迷った際には医療機関や産業医などに相談しましょう。
血圧や血糖値、コレステロール、肝臓、便潜血などは再検査や精密検査の対象となりやすい項目ですが、ほかの項目も含め、検査結果を放置せず、自己判断で受診を遅らせないことが大切です。
広尾クリニック内科・消化器では、定期健康診断・雇入れ時健康診断、生活習慣病健診、特定健康診査のほか、人間ドックを受診していただけます。
再検査・要精密検査にも対応可能なため、二次検診が必要な方はお気軽にご予約ください。