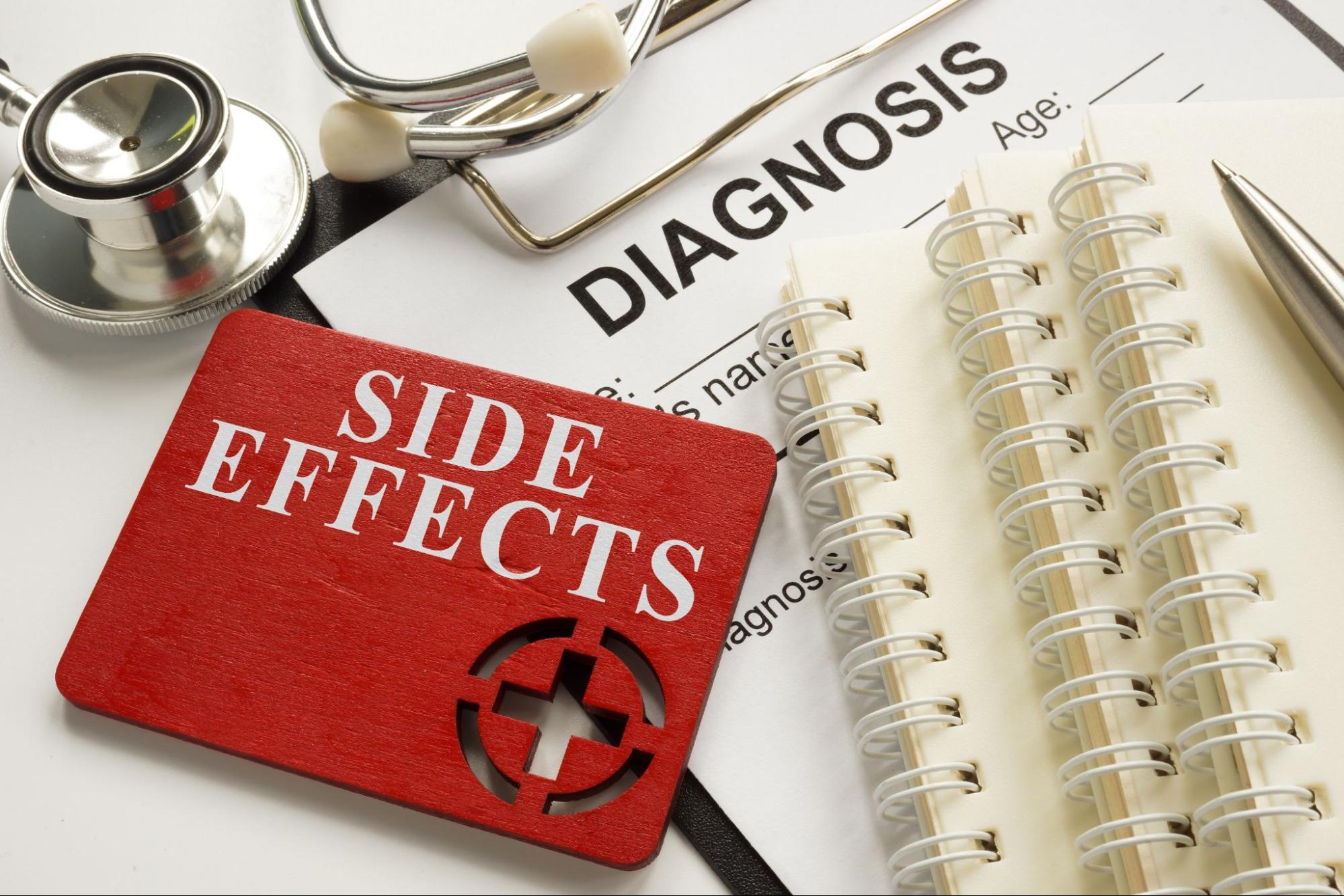
胃カメラ検査(上部内視鏡検査)では、鎮静剤を使用することもあります。
しかし、人によっては鎮静剤の使用や検査時の合併症などについて、疑問を持ったり不安を感じたりしているでしょう。
特に、鎮静剤の副作用や検査後の体調変化、万が一の合併症といった疑問は、検査を受ける前に知っておきたいポイントではないでしょうか。
この記事では、胃カメラ検査で使用される鎮静剤の副作用や合併症のリスク、それらを防ぐための注意点などを紹介します。
不安を軽減し、検査に前向きな気持ちになれるよう、ぜひ記事を参考になさってください。
胃カメラ検査で使用される鎮静剤の副作用

胃カメラ検査で使用される鎮静剤は、患者さんが検査中に感じやすい不安や緊張を和らげ、検査を快適に受けられるようにする効果があります。
しかし、その一方では副作用が発生する可能性もゼロではありません。
ここでは、主な副作用とその対策について紹介します。
薬剤によるアレルギー
すべての薬剤にはアレルギー反応が起こる可能性があり、これは鎮静剤も例外ではありません。
医療機関では検査前に患者さんのアレルギー歴を問診で確認し、過去に何らかの薬剤アレルギーが報告されている場合には、他の薬剤を選択するなどの対応が必要です。
もしも検査中にアレルギー反応が現れた場合には、速やかに適切な処置が取られます。
過去にアレルギー反応を経験した方は、事前に必ず医師にその旨を伝えましょう。
なお、多くの成人の場合、基本的には過去にアレルギー経験がなければ、鎮静剤の使用は問題ないとされています。
頭痛や吐き気
頭痛や吐き気の副作用は、頭痛を起こしやすい体質の人や、低体重の女性に生じやすい性質があります。
医療機関では、事前に患者さんの体質や体重、過去の薬剤反応などをヒアリングし、それを参考に鎮静剤の量を調整したり、より適切な薬剤に変更したりするなどの対応で副作用の予防に努めます。
しかしそれでも頭痛や吐き気が生じた場合には、水分を多めに摂取して薬剤を体外に排出するスピードを速めましょう。
症状が長引く場合や不安がある場合は、医師に相談して適切な処置を受けることも大切です。
眠気
鎮静剤の効果は、胃カメラ検査が終わった後も数十分~数時間にわたって持続するケースがあります。
鎮静剤が代謝されるまでの間、一時的に眠気やだるさ、ふらつきなどの不調を感じることがあるかもしれません。
このような副作用が完全に解消されていない場合、しっかり歩いているつもりでもバランスを崩したり、判断力が低下したりすることがあります。
特に車やバイク、自転車を運転する予定がある場合、鎮静剤を使用する検査は避けるべきです。当院でも検査当日の運転は控えていただいています。
検査当日は無理をせず、できる限り安静に過ごしましょう。可能であれば仕事や趣味の外出は避け、検査後は家で一日休めるようにスケジュールを調整してみてください。
呼吸トラブル
鎮静剤の副作用の中でも特に注意が必要なのが呼吸トラブルです。これは鎮静剤が中枢神経系に作用して、呼吸が浅くなる、または一時的に止まることがある現象です。
特に、以下のような人はリスクが高まります。
- 睡眠時無呼吸症候群
- 夜間にいびきをかく
胃カメラ検査中は、血中酸素飽和度(SpO2)のモニタリング機器を使い、万が一異常があればすぐに酸素を供給するなどの対策を実施します。
呼吸トラブルが起こるリスクを減らすためには、検査前の問診で持病や既往歴を正確に伝えることが重要です。心当たりのある人は、事前の診察時に必ず医師へ伝えるようにしましょう。
血圧の低下
65歳以上の高齢の患者さんは、鎮静剤によって血圧が一時的に低下する副作用について特に注意が必要です。
胃カメラ検査では、検査前後に血圧を定期的に測定し、必要に応じて点滴や薬剤で対応することが一般的です。
医療機関では、検査中も血圧をリアルタイムで監視しているため、異常があればすぐに対応できる体制が整っています。
しかし、事前に血圧や持病について正確な情報を医師へ伝えておけばさらにリスクを軽減しやすくなります。
鎮静剤による副作用は頻繁に起こるものではありませんが、ご自分の健康を守るためにも、持病や健康状態について必ず医師へ伝えておきましょう。
副作用が心配される人の特徴

鎮静剤を使用する際、副作用の可能性を完全に否定できません。そのため、場合によっては鎮静剤の使用を避けたり、検査前・検査後の処置をほかの人よりも重点的に行うことがあります。
特に、以下のような人は鎮静剤の使用に注意が必要です。
- 65歳以上の高齢の人
- 呼吸器疾患を持つ人
- 循環器疾患を持つ人
この条件にあてはまるからといって、必ず副作用が起きるというわけではなく、また胃カメラ検査が受けられないということでもありません。
医師やスタッフが入念な準備をして、細心の注意を払いながら検査を進めたり、患者さんやご家族に検査前・検査後の生活に気を配っていただいたりするなど工夫することで対応しやすくなります。
いずれにせよ、副作用の心配を含め、事前の診察でのヒアリングが重要です。年齢や既往歴などに応じ、医師とともに対応を進めていきましょう。
胃カメラ検査で使用される鎮静剤

胃カメラ検査では鎮静剤を使うことが多いですが、薬剤の種類は複数あります。
ここでは、鎮静剤の目的や種類、使用しない検査などについて紹介します。
鎮静剤はなぜ必要?
鎮静剤は、患者さんの負担を軽減しながら胃カメラ検査を受けるために使用されます。
多くの患者さんは検査時に喉や胃の違和感、検査に対する緊張や恐怖心を感じやすいですが、鎮静剤を使用することでリラックスした状態になり、負担の軽減が可能です。
また、患者さんがリラックスしていると医師が精密な検査をしやすい点もメリットです。
なお、鎮静剤は患者さんを眠ったような状態にする『軽度から中程度の鎮静作用』を持ちますが、完全に意識を失うわけではありません。
必要に応じて医師と意思疎通ができる状態を維持できるため、完全に意識を失う全身麻酔とは異なります。
「完全に眠るのは嫌だな」「全身麻酔はちょっと拒否感が…」という人も、鎮静剤ならほどよい効果で負担を軽減できるでしょう。
胃カメラ検査で使われる主な鎮静剤の種類
胃カメラ検査で使用される鎮静剤は複数の種類があり、患者さんの状態やご希望に応じて適切なものが選ばれます。以下は胃カメラ検査で使われることが多い代表的な鎮静剤です。
| 薬剤名 | 代表的な作用 | 特徴 |
|---|---|---|
| ミダゾラム | 不安の軽減、軽い眠気を誘発します。 | 拮抗薬があるため、効き過ぎた際の素早い対処も可能です。 |
| セルシン | 不安、緊張を緩和します。 | 血管痛を起こすことがあり、検査後も麻酔効果が残りやすいです。 |
選択する際は、医師が患者さんの体調やリスクなどを幅広く考慮した上で決定します。
鎮静剤について不安がある場合は、事前に医師に相談して、効果や副作用について説明を受けてみてください。
鎮静剤を使用しない検査方法の選択もOK
鎮静剤を使用せずに胃カメラ検査を受ける方法もあります。検査内容や方法は鎮静剤を使用する検査と同様です。
鎮静剤なしの検査には、次のようなメリットがあります。
- 検査後すぐに帰宅できる
- 鎮静剤の副作用の心配がない
- 検査当日も車やバイクの運転が可能
一方、デメリットもあるため注意が必要です。
- 喉や胃の違和感を強く感じやすい
- 検査中の不安や恐怖感が軽減されにくい
鎮静剤を使用しない場合は、内視鏡が鼻や喉を通る違和感や不快感を取り除けません。そのような感覚を負担に感じる人もいるでしょう。
また、負担が大きいと身体が緊張してしまい、医師が精密な検査をしにくい状況も考えられます。精密な検査結果を希望するのであれば、鎮静剤の使用を検討してみてはいかがでしょうか。
胃カメラ検査後に考えられる体調変化と注意点

胃カメラ検査後、まれに体調の変化を感じることがあります。
ここでは、検査後に注意したい症状や、その対処法などについて詳しく解説します。
鎮静剤が残ることで起こる症状
胃カメラ検査で鎮静剤を使用した場合、その効果が検査後も数十分~数時間続くことがあります。この影響で、注意力の低下やふらつき、眠気を感じるケースが少なくありません。
しかし多くの場合、これらの症状は一時的に生じるものであり、時間が経てば軽快していきます。それまでは以下のような対処法を取りましょう。
- 検査当日は車やバイク、自転車の運転を避ける
- 検査後は安静に過ごす
- 集中力や重要な判断を必要とする活動を控える
鎮静剤の影響が残っている状態で無理をすると、転倒や事故のリスクが高まります。医療機関へは公共交通機関やタクシーなどを使うか、ご家族の運転による送迎を選びましょう。
また、重要な判断が的確にできない恐れもあるため、そのような活動を避け、安静に過ごすようにしてみてください。
検査後に起こることがある体調不良
検査後には喉の痛みや胸やけを感じることもあります。これは胃カメラが喉を通る際、粘膜が刺激を受けたために起こる一時的な症状です。
また、まれに胃の違和感を覚えることもあります。そのような症状を感じたら、以下のような方法で対処しましょう。
- 温かい飲み物やのどあめなどで喉の粘膜を保護する
- 刺激物(辛いもの、炭酸飲料など)を避ける
一時的な症状のため、多くは時間が経過すれば改善しますが、症状が数日以内に軽減しない・悪化するといった様子が見られた場合には医療機関へ相談し、医師の診察を受けてみてください。
胃カメラ検査後の合併症について知っておきたいこと

胃カメラ検査は高い信頼を得ている検査方法ですが、まれに合併症が発生することがあります。
ここでは、合併症の種類や、合併症が心配な場合の対応方法について解説します。
胃カメラ検査で合併症が発生する可能性は?
胃カメラ検査で合併症が発生する可能性は非常に低いものの、ゼロではありません。まれなケースとして、喉の損傷や消化管の穿孔(穴が開いてしまうこと)、出血などがあります。
喉の損傷は、胃カメラ挿入時に喉の粘膜が刺激され、小さな損傷が生じることにより起こります。検査後に声がれや軽い痛みなどを感じるケースが多いです。
消化管の穿孔は、胃や腸の壁が傷つき、穴が開いてしまう症状です。
出血は、多くの場合は少量です。生検やポリープ切除を行った後、一時的に出血します。ほとんどの人は自然に血が止まりますが、もしも大量に出血した場合は早急な治療が必要です。
このような合併症は発生する確率は低いものの、絶対に起きないとは言い切れません。事前に合併症のリスクや対処法などについて医師から説明を受け、納得してから検査に臨みましょう。
合併症を防ぐための注意点
合併症を防ぐためには、検査前の準備や検査後の過ごし方が重要です。
まず、検査前の診察では医師と時間を取ってカウンセリングを行いましょう。過去の病歴や体調、服用している薬について正確に伝えることで、医師が適切にリスクを把握できます。
検査後の生活については医師やスタッフから受けた説明通りに行いましょう。多くの場合、激しい運動や飲酒をしばらく控え、しっかり休むように言われます。
一般的な注意に聞こえるかもしれませんが、体調悪化や不調のリスクを軽減する方法として効果的です。
まとめ
胃カメラ検査で使う鎮静剤は、患者さんの負担を軽減しながら検査をするために有効な選択肢です。しかし、まれに副作用や合併症が起こるリスクがあります。
このようなリスクは事前の診察時のカウンセリングや、医師やスタッフによる適切な鎮静剤の使用などによって軽減でき、万が一起きた際にも素早い対処が可能です。
鎮静剤の使用は身体と心の負担を両方軽減する効果が期待できます。副作用などの心配ごとについて医師に相談し、疑問や不安を解決してから使用を決定するのもおすすめです。
過剰に心配する必要はありませんが、どうしても使いたくないという患者さんは、鎮静剤を使用しない検査を受けることも可能です。
広尾クリニック内科・消化器では、鎮静剤の使用に疑問やご不安がある患者さんへ詳細な説明をしています。また、鎮静剤を使用しない胃カメラ検査も可能ですので、お気軽にご相談ください。