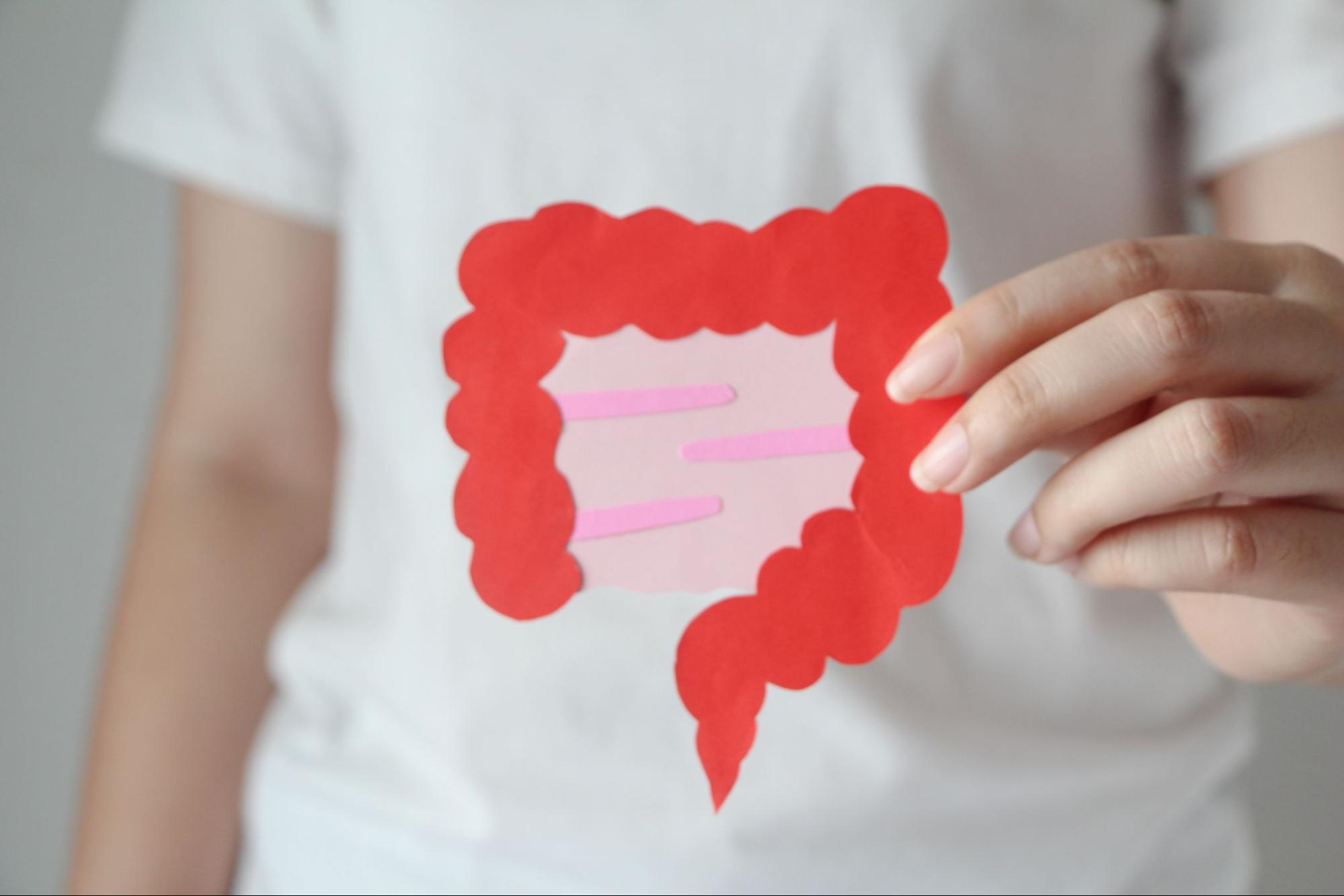
血便が見られると、多くの人が驚き、不安を感じます。
血便の原因は痔のような軽度なものから、胃や腸など消化管からの出血によって起こるケース、大腸がんや潰瘍性大腸炎などの重大な疾患が関係しているケースまでさまざまです。
出血の原因を特定するためには、便の色や状態、併発する症状などを確認し、適切な検査を受けることが重要です。
また、血便の原因によっては、早急な受診が必要になるケースもあります。
この記事では、血便の定義や考えられる原因、診断に用いられる検査方法、受診のタイミングなどについて詳しく紹介します。
血便に気づいた際の対応や医療機関を受診するべき目安を知り、適切な行動を取るための参考にしてみてください。
血便とは

血便とは、便に血液が混じる状態を指しており、その原因はさまざまです。出血の部位や量によって血液の色や混じり方が異なり、病気の手がかりになります。
ここでは、血便の定義や発見のきっかけ、種類について紹介します。
血便の定義
血便は、消化管のどこかで出血が生じ、その血液が便とともに排出される現象です。以下のような特徴があります。
- 出血部位によって血便の色が異なる
- 肛門や直腸など下部消化管からの出血は鮮やかな赤色(鮮血便)
- 胃や十二指腸など上部消化管からの出血は黒っぽい色(タール便)
黒っぽい色になるのは、血液が消化液と混ざって反応するためです。
このほか、目に見えないほど微量の出血が便に混じることもあり、肉眼では確認できない場合でも、何らかの異変を感じた際には注意しましょう。
血便が見つかるきっかけ
血便は日常生活のさまざまな場面で気付くことがあるため、意識的に確認してみることをおすすめします。例えば、以下のようなタイミングは血便に気付きやすいです。
- 排便後に便器の水が赤く染まっていた
- 便の表面に血が付着していた
- トイレットペーパーに血液が付着していた
- 健康診断や人間ドックの便潜血検査で発見された
日常生活の中ではトイレで異変を発見しやすいでしょう。排便後に気になるようなことがあれば、少し注意深く確認してみてください。
また、健康診断や人間ドックで行う便潜血検査は、肉眼では確認しにくい微量な血液も検出可能です。大腸ポリープや大腸がんなどの早期発見につながります。
血便の種類
血便には、出血の部位や状態によっていくつかの種類があります。以下、状態や代表的な出血部位についてまとめました。
| 名称 | 出血部位 | 特徴 |
|---|---|---|
| 鮮血便 | 肛門・直腸など下部消化管 | ・鮮やかな赤色の血液が便に付着している状態 ・痔や裂肛、大腸炎などが原因で見られる |
| 粘血便 | 大腸や小腸など消化器の粘膜 | ・血液が粘液と混じった便 ・潰瘍性大腸炎や感染性腸炎などの疾患で見られる |
| タール便 | 胃や十二指腸など上部消化管 | ・血液が消化液と混ざり、黒色になった便 ・胃潰瘍や十二指腸潰瘍など上部消化管疾患で見られる |
どの便の状態も身体に悪影響が出ている可能性があるため、気付いたら早めの受診をおすすめします。
血便が起こる原因

血便が発生する原因はさまざまですが、どこで出血が起きているかによって病気の種類や症状が異なります。
比較的軽度なものから重大な疾患まで、血便の背後にはさまざまな要因が関係しているため、適切な診断と対応が重要です。
ここでは、血便を引き起こす主な疾患について紹介します。
大腸ポリープ
大腸ポリープは、大腸の粘膜に発生する隆起した組織で、ほとんどは良性ですが、一部は大腸がんへ進行する可能性があります。
多くの場合、ポリープが小さいうちは無症状ですが、大きくなると便が通過する際に擦れて出血し、血便の原因となることも珍しくありません。
出血は少量で、便潜血検査で発見されるケースが多々見られます。ポリープが見つかった場合、がん化のリスクを考慮して内視鏡による切除を推奨します。
大腸憩室出血
大腸憩室とは、大腸の壁の一部が外側に袋状に飛び出した状態のことで、特に高齢者に多く見られる症状です。
普段は無症状ですが、憩室の血管が損傷すると突然の大量出血を引き起こし、鮮血便が見られることがあります。
憩室出血は自然に止血することもありますが、出血量が多い場合や何度も繰り返す場合には、内視鏡を用いた止血処置や場合によっては外科的手術が必要になることもあります。
胃潰瘍
胃潰瘍は、胃の粘膜が傷つき、深い部分まで損傷が及ぶ疾患です。主な原因としては以下が考えられます。
- ピロリ菌に感染している
- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の長期使用
- 精神的ストレス
- 食生活の影響 など
胃潰瘍が進行すると血管が傷付き、出血を伴うことがあり、血液が消化液と混ざることで黒色のタール便が見られるようになります。
胃潰瘍による出血が続くと貧血を引き起こすこともあるため、長引く場合には内視鏡検査による診断と治療が必要です。
ピロリ菌の除菌や胃酸の分泌を抑える薬を使用した治療が中心になります。
十二指腸潰瘍
十二指腸潰瘍は、胃潰瘍と同様に粘膜が損傷して潰瘍が形成される疾患です。主な原因はやはり胃潰瘍と同様に、ピロリ菌感染やNSAIDsの長期使用とされています。
十二指腸潰瘍による出血も、消化液と混ざって黒いタール便として現れることが多く、進行すると貧血や吐血などの症状を伴うこともあります。
症状が重い場合には、内視鏡による止血処置や入院治療が必要です。胃潰瘍と同じく、ピロリ菌の除菌治療や胃酸分泌抑制薬の使用が一般的な治療法です。
感染性腸炎
細菌やウイルスが腸内に感染し、炎症を引き起こす疾患です。主な原因菌としては以下が代表的です。
- カンピロバクター
- サルモネラ菌
- 病原性大腸菌 など
感染性腸炎では、腹痛や下痢、発熱とともに血便が見られることがあり、特に細菌性の場合には粘血便を伴うことが特徴です。
治療では、原因となる細菌やウイルスに応じて適切な抗菌薬の使用や、症状に合わせたケアが行われます。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に慢性的な炎症が生じ、びらんや潰瘍が形成される炎症性腸疾患のひとつです。
原因は明確には解明されていませんが、免疫異常が関与していると考えられています。
症状として、血便や粘血便、腹痛、下痢が繰り返し発生し、進行すると貧血や体重減少を伴うこともあります。
潰瘍性大腸炎は再発を繰り返すことが多い難病で、治療には抗炎症薬や免疫調整薬が用いられます。また、治療と並行し、生活習慣の見直しが必要になることも少なくありません。
痔
血便の原因としてよく見られるのが痔です。特に切れ痔やいぼ痔では、排便時に鮮血が見られやすく、トイレットペーパーに血が付着するケースが多いです。
痔による出血は比較的軽度ですが、痛みを伴うこともあり、慢性的に続く場合には治療が必要です。
軽症の場合は、生活習慣の改善や外用薬で対応しやすいですが、重症化すると手術が必要になることもあります。
排便時に発見しやすいため、異変を感じたら注意深くチェックしてみてください。
また、出血の原因が痔以外の場合も考えられます。「ただの痔だから大丈夫」と軽く考えず、早期の受診がおすすめです。
大腸がん
大腸がんは大腸の粘膜に発生する悪性腫瘍で、進行すると血便や下痢・便秘の変化、腹痛などの症状が現れます。
しかし、初期には無症状のことが多く、進行するまで気付きにくい特徴があります。
出血は微量で、便に血が混じっていても肉眼では確認しづらいため、早期発見には健康診断や人間ドックで実施されている『便潜血検査』が有効です。
大腸がんが疑われる場合には、大腸内視鏡検査を行い、必要に応じて組織を採取し病理検査が実施されます。進行がんの場合は手術や化学療法が選択されることもあります。
血便の原因を突き止める検査方法

血便の原因を特定するためには、適切な検査が必要です。血便の状態や症状に応じて、さまざまな検査を行います。
ここでは、代表的な検査方法について紹介します。
便潜血検査
便潜血検査は、便の中に肉眼では見えない血液が混じっているかを調べる検査です。
大腸がんやポリープの早期発見に役立つことから、健康診断や人間ドックでも実施されています。
ただし、便潜血検査で陽性になった場合でも、必ずしもがんや重大な疾患があるとは限りません。精密検査として大腸カメラ検査などが推奨されることが多いです。
大腸カメラ検査(全大腸内視鏡検査)
大腸カメラ検査(全大腸内視鏡検査)は、肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体を直接観察する検査です。
大腸ポリープやがん、炎症などの異常を発見することが可能であり、必要に応じて組織の採取(生検)やポリープの切除も行われます。
腸内を空にする前処置が必要ですが、詳細な診断ができ、さまざまな病気の早期発見につながる方法です。
S状結腸内視鏡検査
S状結腸内視鏡検査は、大腸カメラ検査の一種であり、観察範囲がS状結腸と直腸に限定されるものです。
血便がS状結腸や直腸からの出血であると疑われる場合、短時間で実施できるため、患者さんの負担が少ないというメリットがあります。
特に痔や直腸ポリープ、S状結腸がんの疑いがある場合に有効です。
ただし、大腸の奥に異常がある場合には適していないため、必要に応じて全大腸内視鏡検査が実施されます。
胃カメラ検査
胃カメラ検査は、口または鼻から内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸を直接観察する検査です。血便の中でも黒いタール状の便(タール便)が見られる場合、上部消化管の出血が疑われるため、この検査が推奨されます。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がんなどの診断に有効であり、必要に応じて組織の採取(生検)や止血処置が行われることもあります。
胃カメラ検査には苦しいイメージをお持ちの方が多いですが、鎮静剤を使うことでリラックスした状態で検査を行うことも可能です。
こんな症状はすぐに受診を

血便が見られた場合、すべてが重大な病気に直結するわけではありません。しかし、中には早急な治療が必要なケースもあるため、症状によっては速やかに医療機関を受診することが重要です。
特に、血便に加えて腹痛や貧血症状がある場合、消化管からの出血が疑われ、放置すると危険な状態になる可能性があります。
ここでは、受診を検討すべき症状や、『血便緊急外来』の利用が推奨されるケースについて紹介します。
早めの受診を推奨する代表的な症状
血便が出たからといって、すべてのケースが重病ではありませんが、可能な限り早く治療を開始するべき病気が疑われる場合もあります。
患者さんご自身では判断が難しいことも多いため、以下のような便やお腹の様子が認められた時には、できるだけ早い段階の受診をおすすめします。
- 血が混ざった便が出た
- トイレットペーパーに血液が付いていた
- 黒い便が出た
- 便がすべて出ていない感覚が残る
- 便秘・下痢が長く続く、繰り返す
- 便に粘液が付いている
- 腹痛が続く
- 細い便が出るようになった など
便のことで受診することに恥ずかしさを感じる人もいるかもしれませんが、場合によっては大腸がんをはじめ、難病のサインである可能性が否定できません。
「便やお腹の調子がおかしいな」と感じたら、ぜひ医療機関で受診してみてください。
『血便緊急外来』も検討を
血便緊急外来とは、可能な限り早く診断や治療をするための専門外来で、緊急性が高い血便症状が見られた患者さんを対象にしています。
便やお腹の状態によっては、血便緊急外来での受診もぜひ検討してみてください。特に以下のような場合、受診を強くおすすめします。
- 排便に鮮血が混じっていた
- 血便だけではなく、貧血も感じる
- 血便だけではなく、腹痛もある
このほか何らかの異常を感じているものの、自分では血便緊急外来を受診するべきかどうか判断できないという場合、まずは問い合わせをしてみましょう。
また、可能であれば血便の写真を撮影しておいてください。医師が見て確認し、適切な診断をする重要な情報になります。
まとめ
ただ血便といっても、原因や種類が複数あり、関わる疾患もそれぞれ異なります。大きな病気が隠れていることもあり、ご自分では判断しにくいということも少なくありません。
血便が出たり、便の状態やお腹の具合に異常を感じたら、できるだけ早めの受診を心がけてみてください。
また、『便に鮮血が混ざっていた』『血便に加えて貧血症状もある』『血便とともに腹痛もある』などの場合、緊急性が高い状態の可能性が高いです。その際には『血便緊急外来』の受診をおすすめします。
広尾クリニック内科・消化器では、血便で分かる身体の異常を見逃さないよう、丁寧な検査を行っています。
また、血便緊急外来の体制も整えており、可能な限り早い診断や治療の開始を心がけています。便やお腹に異常を感じたら、ためらわずに受診をご検討ください。